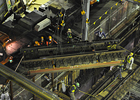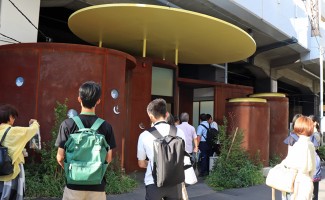渋谷文化プロジェクト
MENUKEYPERSON
震災を乗り越え、東北発のソウル&ビートを渋谷から世界へ
三絃・津軽三味線&ドラム・パーカッション天地人
 プロフィール
プロフィール
天地人
2003年に大間ジローの呼びかけにより、大館曲げわっぱ太鼓の大沢しのぶ(2013年1月31日に卒業)、津軽三味線奏者の黒澤博幸の3人で、津軽三味線&打楽器ユニット「天地人」を結成。2011年3月11日以降、200回以上の復興支援コンサートを国内外で精力的に活動をする。現在、結成10年周年記念ツアー「KADODE2013〜新しい旅立ち〜」を展開中。
http://www.tenchijin.info/
大間ジローさん
1954年、秋田県小坂町生まれ。ビートルズに憧れてバンド活動を開始し、18歳で上京。73年、「ザ・ジャネット」としてプロデビュー。解散後、76年に21歳で「オフコース」にドラマーとして参加し、「さよなら」「YES-NO」などの数々のヒット曲で知られる。解散後、95年から故郷秋田に移住。99年には元オフコースのメンバー清水仁、松尾一彦とユニット「ABC」を結成しライブ活動を開始。現在、バンド活動のほか、イベントプロデュースなど多方面で活躍の場を広げている。
黒澤博幸さん
1972年、岩手県盛岡市生まれ。7歳から三味線を習い始め、中学生で料亭などでの演奏経験を積む。白川流津軽三味線奏者の井上勇美人(ゆみと)氏や、巨匠・高橋竹山氏のテープを聞きながら津軽三味線を独学で学ぶ。2002〜2004年、「津軽三味線全日本金木大会」で最高賞である「仁太坊賞」を3年連続獲得し、名実ともに若手実力派として注目される。現在、弟子の指導にあたるほか、様々なミュージシャンとの競演にも積極的に取り組み、幅広い音楽活動を続けている。
「あばらの骨を折るぐらい、三味線を極致まで叩き叩き続ける」――津軽三味線界の鬼才と呼ばれる黒澤博幸さん。その攻めの姿勢で畳み掛けてくる黒澤さんを、親子ほど年齢の離れた元オフコースのドラマー・大間ジローさんが真っ向勝負で受け止める。お互いに譲らない、その丁々発止のせめぎ合いが音魂(オトダマ)として、言葉や国境を超えて多くの人びとの心に夢や元気を届ける。今回のキーパーソンインタビューでは、結成10年周年を迎えた東北発の津軽三味線&打楽器ユニット「天地人」の大間さんと黒澤さんにご登場いただき、ユニット結成までの経緯からインストが持つ魅力、さらには11月に開催を予定する「第8回渋谷音楽祭」への参加に至るまで、お二人に熱く語っていただきました。震災の悲しさや苦しさを通じ、東北出身のお二人が感じた「音楽の力」とは一体何だったのでしょうか。
名曲喫茶ライオンにショック!東北とのギャップがすごくて。
_ズバリ渋谷は好きですか?また渋谷の印象を教えてください。
大間:もちろん好きです。1973年、秋田から上京して間もなく、新宿・伊勢丹でロックのコンテストに出ました。そこで準優勝したのをきっかけに、僕の音楽人生が始まったんですが、そのデビュー当時の事務所が宇田川町、東急本店の先にありました。どうも新宿は怖くて馴染めなかったのですが、渋谷にはそういう感じは全くなくて。駅から事務所までよく歩いていきましたが、70年代初頭の渋谷の街は若者文化とか、クリエイティブな雰囲気などが漂っていました。
黒澤:自分が渋谷に初めてきたのは、20代前半のころ。NHKホールの民謡フェスティバルに出演するためですが、道すがら街行く人びとを見てカルチャーショックを受けました。それまで、岩手から外に出ることがなかったし、東京で仕事があっても国技館など下町っぽいところが多かったので(笑)。今は天地人の事務所が渋谷にあるので、ちょくちょく来るようになりましたが、渋谷ヒカリエなど、どんどん新しいものが誕生し、情報を流すスピードがすごくて驚いています。

大間:渋谷の街は、本当に来るたびに「ここに、こんなのあったかな?」という発見があったりして。何カ月来ないともう変わっている印象です。事務所が宇田川町あったこともそうですが、オフコース加入前に活動していたバンド「ジャネット」の解散コンサートも公園通りにあった小劇場「渋谷ジァンジァン」でした。それから、僕は秋田県大館の付近で生まれたのですが、大館はハチ公の故郷なので、なんだか秋田と渋谷がつながっているような、そんな不思議なご縁を感じています。
黒澤:ただ自分の場合、津軽三味線で作曲しながらリズムを作って弾くという世界なので、田舎の味を失いたくないという気持ちもあります。もともと三味線は、山も川もある田舎で生まれてきた音楽なので、それを産地直送で届けたい。と同時に両極端なのですが、渋谷から新しい三味線の世界も開拓していかなきゃいけないという使命も持っています。
_渋谷で行きつけのお店などはありますか?
大間:以前までは渋谷に来るたびに、ヤマハに行っていましたけれど、残念ながらヤマハはなくなりました。僕の音楽の原点みたいな場所だったので、とても寂しいです。

黒澤:自分は、よく焼き鳥屋に行きます(笑)。道玄坂小路にある40年も50年もやっている老舗の森本さん。今風のところってなかなか一人では入れないので、一人で入れる、サラリーマンと横に座って一緒に飲んで仲良くなるという。結構、年の割には僕、古いので(笑)。それから、百軒店にある名曲喫茶ライオンもよく行きます。ここに入ったときは、すごくショックでしたね。だってライオンは昭和元年の創業ですよ。僕がやっている津軽三味線を起こした始祖の仁太坊さんが亡くなったのが、昭和3年です。その頃、東北の唯一の娯楽といえば、新潟から瞽女(ごぜ)と呼ばれる盲目で門付巡業をする女性旅芸人くらいで、名曲喫茶とのギャップがすごくて。本当に同じ国だったのだろうかって(笑)。
大間:今度、連れてってください。

黒澤さんが「カルチャーショックを受けた」という、道玄坂・名曲喫茶ライオンの前で
三味線を全力で叩き、あばらの骨を折る。そのプレーは凄かった。
_音楽のお話をうかがっていきたいと思いますが、まず、お二人が出会ったきっかけを教えてください。
大間:2001年にテレビ岩手のプロデューサーから「ぜひ、ジローさんに紹介したい三味線弾きがいるので」といって、楽屋に黒澤さんを連れてきたんです。僕は三味線とか全然分からなくて「ああ、こんにちは。はじめまして」みたいな感じだったのですが、そのプロデューサーから「ジローさんのロック的なドラムとたぶん合うと思う」と薦められまして。
黒澤:その次の年ですね。

大間:一度顔合わせをして、セッションしたんですよ。三味線とは初めてでしたが、やっぱり東北人ですから、生まれ育ったルーツの中に民謡やお囃子とか、神楽とかがあったので違和感が全くありませんでした。どちらかといえば、黒澤さんはあったかもしれまんが…。
黒澤:いいえ(笑)。初めてのセッションでは違和感や緊張というよりも、どうやって自分が携わっていくべきかどうかなと。太鼓がいてドラムがいて、メロディ楽器は自分のみだったので、何をどうすればいいのかなと模索する状態でした。
_「天地人」結成時は和太鼓を含めた3人だったそうですが、どんなジャンルの音楽を目指したのですか?
大間:僕と黒澤さんのほか、化学反応を期待して和太鼓奏者の大沢しのぶさんを含めた3人で始めました。案の定、1+1は2じゃなくて、4とか5の変化が出てきたんです。ただ、三味線は太鼓とドラムの音圧に負けてしまうので、もう黒澤さんは全力投球で負けじと叩く叩く、叩き三味線を極致まで弾くわけです。あるときは、あばらの骨を折ったぐらい、そのプレーには凄みを感じました。
黒澤:初めは1曲5、6分が、気がついたら15分とか、結構ざらで(笑)。

大間:ジャズミュージシャンみたいなアドリブの応戦というか、二度と同じことができない即興演奏が多かったですね。顔を合わせると、「よし!」と集中して、その中でモードをつくっていく感じでした。ロックや民謡、ジャズなど、様々な要素の音楽をクロスオーバーし、それぞれが融合できるかという…。いつも言っているのですが、和と洋の調和は、それぞれルーツが全く違います。それぞれが音を出すことで、音と音のせめぎ合いが起こります。僕たちの音楽はそれを楽しみながら構築し、いかにそれを分かりやすく伝えていくかということだと思っています。
黒澤:でもドラムと太鼓を相手にすると、どうしても負けちゃう。そこで、いろいろなミュージシャンやエンジニアからアドバイスしてもらい、自分でカスタムした日本に1挺しかないエレキ三味線をつくったんです。三味線のアナログの魅力をいかにデジタルにして面白く伝えられるか。やるからにはアナログの良さを引き立ててくれる、そういうふうなものにしたいと思っています。
英語圏でもイスラム圏でも…、天地人の強みはインストの音魂
_国内のほか、海外でも積極的にライブを展開されているそうですが、その手応えはいかがですか?
大間:オフコース時代にも海外進出にトライしたことがあります。英語バージョンをつくったり、向こうにも何度か行ってすべて英語のアルバムを作ったりして、いいところまでいったんですが、やっぱり英語力の壁というのかな。小田和正さんはとても英語が達者な人なんですが、それでもネックがあったと思うんですよ。オフコースの魅力は、歌詞だったり声だったりするので、それが上手く伝えられなかった。ところが、天地人の強みはインストゥルメンタルであること。英語圏でも、スペイン圏でもイスラム圏でも……。音魂(オトダマ)というか、音で伝えていきますから。その可能性をフランスでも、ドイツでも、アメリカに行ったときにも感じました。

黒澤:そう、インストの強みはあります。国内だと「CDを出しても、インストは売れませんよ」と言われたりもする。でも、ライブに来たお客さんから「何か忘れていたもの、失いかけていたものが甦ってきた」と言われたりして。それって、きっと日本人だけじゃなくて外国人だって一緒だと思います。自分たちが弾いた音を、お客さんが自ずと考えて、それぞれの答えを出してくれます。YMOの「ライディーン」も言葉のない楽曲だったから、海外で成功したんじゃないかと思います。
若い人が「民謡が聞きたい」、全てを失い原点に戻る気持ちが湧く
_東北出身のお二人にとって東日本大震災は忘れられない記憶だと思いますが、震災を経て「音楽の力」をどう感じていますか?
大間:「ライブをしに来てくれ」と言われても、震災直後はすぐには行けなかったです。「音楽に何ができるんだろう?」という自問自答の気持ちもあったし、まずは食べること、住むことが先だろうと思っていたので。僕らが行っても、何も出来ないんじゃないかなと思っていたので。
黒澤:そうですね。自分は震災後、すぐに被災地に向かい、とにかく音楽よりも今日、明日、暮らす人たちをどうやって助けられるかということばっかり考えていました。ましてや、自分は電気を使う仕事なので「こんなときに音楽で電気使っている場合じゃないでしょう」という気持ちもありましたし…。ただ、もともと津軽三味線は、御霊供養みたいな部分が元なんですよ。東北で亡くなった御霊は必ず恐山に行ってから極楽浄土と言われているのですけれど、三味線を弾いて亡くなった人を供養する意味があります。いつかは御霊供養を込めて弾きに行かなければいけない、という思いはありました。
大間:そうだよね。

黒澤:そんなとき、「避難所の体育館にはピアノが一個しかなくて、朝のラジオ体操の生ピアノが唯一の音楽だから、もし良かったら三味線を弾きに来て欲しい」と誘われて、白い花をいっぱい車に積んで棺がまだ間に合っていない遺体の仮置き場みたいなところに行き、三味線を弾きました。避難所に集まったみんなに「なにを聞きたい?」と聞くと、若い人もいたんですけれど「とにかく民謡が聞きたい」って。今まで民謡を聞いたことがない若い人たちがですよ。今思えばね、全て失って全てがリセットされて、そういう原点に戻るような気持ちが湧いてきたのかなと思う。お客さんは300人くらい、マイクもない場所で、震災の傷跡が生々しくて悔しくて泣きながら三味線を弾いていたら、その時に助けてくれたのが小学校の子どもたちでした。民謡を聞いた子どもたちが、サランラップとかボックスティッシュの箱を持って、まるで三味線を弾くような真似事をして騒いでくれて。それを見た避難所の人たちが、みんな大笑いして空気が和んだんですよ。その姿に自分たちはすごく助けられて、ここに来て良かったとしみじみ感じました。これも音楽の力の一つなんじゃないかと思います。

天地人のライブの様子