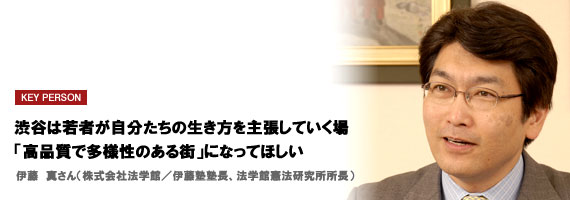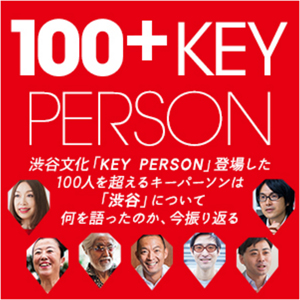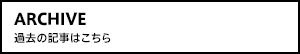1995年、渋谷・桜丘町に司法試験塾を開いた伊藤真さん。今では、公務員試験や司法書士・行政書士・宅建の資格試験などもサポートする総合塾として、全国にその名を馳せている。法曹界を目指す受験生から「カリスマ」と呼ばれる伊藤さんに、渋谷の街について伺いました。
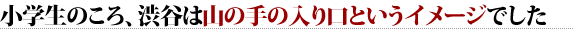
--渋谷の街と最初の出会いはいつごろでしたか?
やはり東急のプラネタリウムです。小学校のころだと思います。住んでいたのは東京の下町でしたが、渋谷は下町からすると違った香りのする雰囲気を子供ながらに感じました。都電に乗ってデパートのある渋谷に来るとなると、かなり違う世界。下町のガキ大将からすると憧れでしたね。小学生のころは、渋谷というと山の手の入り口というイメージでしたが、もう少し具体的な形になってきたのは、高校に通うようになってからです。1974年に、学芸大学付属高校に通うようになり、当時住んでいた千代田区から学芸大学まで毎日電車で通うようになりました。そうすると渋谷で東横線に乗り換えないといけないので学校帰りに渋谷で遊ぶようになりましたね。高校のころ初めてデートしたのも松濤の鍋島公園でした(笑)。やはり、憧れの場所というのは昔から渋谷でしたね。
--学生時代、渋谷ではどんな過ごし方をしていましたか?
そうですね。映画見たり、パルコ等で買物したりしました。桜丘町の方は、まだ小さな飲み屋があったりした時代で、まだ高校生だった自分たちにはちょっと遠い感じがありました。東大に入って駒場に通うようになりましたが、天気のいい日には駒場から歩いて、松濤や東急の本店だとかを抜けて帰ったりもしましたし、当時ブームだったディスコにも行きました。六本木にも行きましたが、やはり遊ぶ場所は渋谷が中心でしたね。ちょっと背伸びをして遊ぶ場所?そんな感じもありました。

--そういう意味では、渋谷との付き合いは長いですね?
ただ仕事をやるようになってから、渋谷からちょっと離れていました。1995年に法学館を立ち上げるのですが、その時にまずどこに学校を作ろうかと考えました。当時、専門学校が集まっている場所というのは、水道橋・お茶の水の界隈と、高田馬場でした。学生たちが集まる大きな拠点がその2カ所だったわけですね。当時渋谷はほとんど学校もなく、勉強するポイントではなかったが、でもやっぱり渋谷が重要じゃないかと思いました。渋谷には当時専門学校の拠点は無いのですが、東大の駒場キャンパスや青学がありますし、東横線一本で慶応の学生も来る。法律家の養成の場としては、渋谷がちょうど空白地帯だった。誰も手を付けていない場所だったんですね。高田馬場は早稲田のバンカラなイメージがあるので、逆にちょっとハイセンスな学生、背伸びした学生などで法律家になる志を高く持っている学生たちが集まれる新しい場所や新しい法律家のイメージを作りたかった。
司法試験は当時、ねじりハチマキとか、暗くジメジメしたイメージが定着していたんですよ。そうじゃなくて、もっとかっこよく勉強できるだろうと思い、そして将来のビジョンも世界を視野に入れて自由なスタイルで勉強してもいいんじゃないのかと、固定観念にとらわれない新しい発想で学校を作りたかったわけです。我々の塾のモットーが「合格後を考える」。試験のことだけを考えるのではなく、合格した後になにをやるのか、そこから何を世界に向けて主張し、発信し、飛び立っていくのかを常に考えろということです。そして合格までの過程も人生の一部なので、例えば勉強しているその時でも幸せを感じられるような勉強の仕方があるんじゃないのか。合格した瞬間に幸せになって、それまでは苦痛でしかないというような生き方は違うんじゃないのかと…。勉強していく過程やプロセスも自分の人生の立派な人生の一場面なんだから、より幸せを感じながら勉強ができる。そういう充実した日々を過ごせれば、仮に不合格でもその過程はすごく役に立つはずです。こういうまったく新しい勉強スタイルにふさわしいのが渋谷の雰囲気やイメージだった。物件探しには苦労しましたが、偶然さくら通りにいい物件が見つかった。そのときは本当に、「求めれば与えられる」と思いましたね。

ドラマの撮影などでも使われる法廷教室