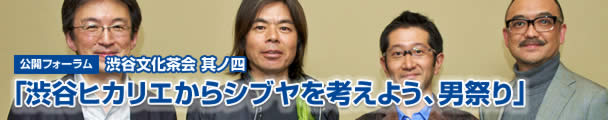
青学生は絶対に中を通りますよね、間違いなく。
西:続きまして「アーバンコア」について。ご存じのように渋谷駅は谷底地形で高低差があり、宮益坂側のヒカリエは、明治通り沿いのヒカリエの2階とか3階と同じ高さになります。地下の副都心線から含めると、かなりの高さを人が縦に移動することになりますが、ここをいろいろと工夫されたということで。「教えて!分かる人」にアーバンコアという動線について教えてもらおうと思います。

JR渋谷駅からつながる跨道橋など、回遊性の高い街づくりを目指す
宇留間(教えて!分かる人):アーバンコアは、地下3階から4階までの吹き抜けを中心にした空間・動線のことです。ヒカリエの吹き抜け地下3階は副都心線、今後は東横線の駅とつながる部分になります。1階は明治通りとつながり、2階はJR渋谷駅から伸びる「跨道橋(こどうきょう)」と呼ばれる歩道橋へとつながり、2階を逆方向へ進むと、宮益坂のちょうど中間ぐらいに出るルートにつながっていきます。3階からは青山通りへと抜けることもできます。4階は将来的にデッキができる予定で、これも渋谷駅につながりますので、アーバンコアの縦動線を使うと坂を苦にせずに渋谷の街を移動していただくことができます。
西:3階を突き進むと宮益坂の上の辺りに到着するような感じなんですね。
宇留間(教えて!分かる人):この写真は青山通りから撮影したものです。
西:さっき、山口さんがメカゴジラっぽいとおっしゃっていた後ろ姿ですね。ヒカリエの後ろ、かなりボリューミーな感じですね。
渡辺:あそこに出るんだ。
西:もう一つ、坂の途中、渋谷郵便局の横断歩道を渡ったあたりに横から入れる入口もありますね。
宇留間(教えて!分かる人):はい。ちょうどヒカリエの2階部分になります。
西:郵便局までは、ほとんど雨に濡れずに行ける感じで。
宇留間(教えて!分かる人):そうですね。JR線や東横線をお使いのお客さまは、2階の跨道橋を通ってヒカリエの貫通通路を抜けていきますと、渋谷郵便局の辺りに出てきます。

渡辺:青学生は絶対に中を通りますよね、間違いなく。
西:これが通学路になりますね。
山口:今まで割と地味と言えば地味なエリアだったから。この導線を通してエリアが活性化されるような気もしますね。
西:青学は今年から、4年生が青学キャンパスにまた戻ってきますからね。今まではほんとに静かなところでしたが、4月になったらにぎやかな場所になってくるんでしょうね。
エスカレーターがサイネージリングの中を通っていくというイメージです。
西:僕らどうしても縦に目がいくんですが、渋谷ヒカリエの横の面白さも体感してみたくなります。それと同時に「デジタルサイネージ」も、結構力が入っていると伺っています。アーバンコアを軸に新しいかたちのデジタルサイネージを導入するということですが。
小林(教えて!分かる人):アーバンコアは、お客さまが電車で渋谷に来たときに一番初めの玄関口になる空間です。ヒカリエではエスカレーターで地下3階から4階まで上がるのに2分位かかりますので、この空間、時間を楽しく感じてもらうためにデジタルサイネージを企画しました。サイネージは吹き抜け空間を活かしたリング状で、合計3本あります。エスカレーターがサイネージリングの中を通っていくというイメージですね。
西:すごい。

最大で直径約17メートルの円形LED サイネージが3 本設置される。
小林(教えて!分かる人):たとえば、2階のサイネージは重さが10トンぐらい、円周としては50mぐらい、かなり大きいものになっています。それを下から柱で支えてしまうと非常に重たいというか、野暮ったいものになってしまいますので、いかにサイネージを軽やかに見せるか、というところが難しかったですね。
西:その輪の中をエスカレーターが通っていく…。
日比野:ここは、今もう見えてるよね。
小林(教えて!分かる人):点灯していないだけで、もうデジタルサイネージは完成しています。
西:現在ここに流すコンテンツをどうするかということを、小林さんが考えているところなんですか。
小林(教えて!分かる人):そうです。
「俺も作りたい」とか「発想やイメージが湧いた」っていう場所になればいい
西:今度はちょっとコンテンツの方を見て行こうと思うのですが、6階・7階にある「飲食フロア」の上にはクリエイティブスペース「8/」というフロアがあります。8スラッシュと書いて、「8/(はち)」と読むんですが。こちらは、かなり独自の企画がたくさん詰め込まれていまして、たぶん男性の利用も非常に多くなるじゃないかと思われます。(教えて分かる人)小林さん、ご紹介いただけますか。

小林(教えて!分かる人):非常に説明しづらいフロアなんですが…、デザインとアートの拠点みたいなものをつくりたいと考えています。真ん中に150平米ぐらいのイベントスペースがあり、それを取り囲むようにギャラリー、カフェ、ラウンジといった機能を設けて複合的なアートスペースをつくっていきます。一緒に運営するパートナーには、ナガオカケンメイさん、小山登美夫さんがいらっしゃいます。ナガオカさんは47都道府県、それぞれからその土地の元気のある人とか、デザイン性の優れた器とか、そういうものを47個持って来て展示します。最近、(ナガオカさんは)各県を3カ月ぐらいずっと取材をして、それを雑誌にまとめています。今5冊ぐらいになっているそうですが、ライフワークとして10年ぐらいかけて完成させていきたいそうで、その一つの拠点がここになります。47個のテーブルを並べ、常設と年間数回の企画を展開していくことが決まっています。
日比野:そこにはショップではないんですか?
小林(教えて!分かる人):47個のテーブルに並べられたものは、基本的に全て買えます。
日比野:はい。
小林(教えて!分かる人):小山登美夫さんは、現代アートのギャラリストとして、アートの裾野を広げたいという思いをお持ちの方です。「8/」では小山さんご自身が抱えていらっしゃるアーティストにとどまらず、幅広いアーティストを紹介していただける予定です。オープニングは世界的アーティストのダミアン・ハーストの展示を開催予定で、以降もご本人が「いま一押し」というものを紹介していく場所になります。またフロアの真ん中は「コート」というイベントスペースで、ワークショップやトークショーみたいなことを頻繁にやっていこうと考えています。実は日比野さんにもいろいろご相談をして、ユニークなご提案をいただいているところです。

西:コートは、イベントに使わないときはどうされるんですか?
小林(教えて!分かる人):通常時はソファを置き、ラウンジみたいにどなたが来てもゆっくりできる場所になります。
日比野:例えば10代でも、そこで何かできるという装置にしていくことができれば、渋谷のクリエーターにとっては「8/」が要の場所になってくると思うんですよね。ナガオケンメイさん、小山登美夫さんのスペースから、「モノづくりって楽しいな」という匂いがフロアに充満する環境になると思うので、このコートで「俺も作りたい」とか「これをきっかけにして、何か発想やイメージが湧いた」っていう場所になればいいと思います。何かを作るときはゼロから生まれるものではなく、何かきっかけがあったり、核があったりして、それにまゆが糸を巻くようにしていろいろ形になっていくものだと思うので。そういう風に上手いこと周りのショップと連動していけると、いいなと思います。
小林(教えて!分かる人):おっしゃるとおりです。渋谷にはこういうフリーなスペースというか、表現する場所があんまり無いんです。せっかくこういう新しいビルができるので、渋谷の真ん中に未完成な部分をつくりたいなと思って、あえて何も設定しないスペースにしています。
日比野:偉いよね。
西:50坪以上もある広さですからね。そういう意味では、ここの空間をどうソフト的に運用していくかということが、未来の渋谷を少しずつ変えていくかもしれませんね。

フロア中央の「コート」ではトークショーやワークショップなど様々なイベントが催される。
小林(教えて!分かる人):渋谷にはコンテンツはたくさんあるので、それらの表現の受け皿になればいいなとは思っていますね。
西:楽しみな空間ですね。山口さんどうですか。
山口:非常に興味深いです。渋谷や原宿では昔からちっちゃなアパートなんかを若い人たちがシェアしたり、事務所を構えたりして、裏道にどんどんブランドショップができた歴史がありますよね。そうして渋谷から原宿にかけての消費がぐわーっと広がっていったと思うので、そういう何かを生み出す空間が渋谷のど真ん中にあるというのは、僕はすごくいいなと思います。
西:「8/」楽しみですね。スペース名と階数が一致していますから、分かりやすいですし、僕も足を運んでみたいです。
ベンツのSクラスまで、エレベーターに乗せることができます。
西:それから「8/」の上、9・10階には「(ヒカリエ)ホール」という広大な空間があります。ここはどういうかたちで使われるのか、(教えて!分かる人)宇留間さん、教えてください。

宇留間(教えて!分かる人):9階・10階には1,000平米と300平米の大小二つのイベントホールがあります。通常イベントホールは1階や地下の低層階にあるケースが多いんですが、このホールは中層階にあり、ガラス面からは渋谷の街全体を見下ろすことができます。ホールの天井高は7m、ファッションショーや車の展示会等々に広くご利用いただけるスペースです。
西:はい。
宇留間(教えて!分かる人):渋谷駅前キューフロントのデジタルサイネージ「キューズ・アイ」とホールを連動させて、ホールで行うイベントの様子をほぼリアルタイムでキューズ・アイに流したりもできます。渋谷の街全体を使ったプレゼンテーションの場として、ぜひ多くの方々にご利用いただきたいと考えています。
西:かなり広大な空間ですね。
宇留間(教えて!分かる人):開業イベントとしては、市川亀治郎さんが6月に四代目市川猿之介を襲名されるのを記念した大博覧会が開催されます。また6月30日には「TEDxTokyo2012」という、討論を中心としたイベントを開催します。2009年から東京で開催されている世界的なイベントが、今年は渋谷ヒカリエで行われることが決まっています。

世界的なクリエイティブイベント「TEDxTokyo2012」が渋谷に上陸する。
西:発表はまだだと思うんですが、「TEDxTokyo2012」で大物のスピーカーの方が来られる可能性がおおいにあるわけですね。
宇留間(教えて!分かる人):そうですね。今その部分について、調整をしております。
西:先ほど、車の展示会と言っていましたが、車も大型エレベーターで上まで搬入できるんですか?
宇留間(教えて!分かる人):ベンツのSクラスまでは、エレベーターに乗せることができます。
西:ホールも「8/」も、魅力なソフトがここから次々に出てきそうですね。ちょっと駈け足ですが、渋谷ヒカリエの情報は、今まで、いろいろなところからバラバラに耳にする機会はありましたが、これだけ集中的に担当者からお話しを聞くことができ、今日はかなり濃密にヒカリエの情報をインプットできたのではないでしょうか。

会場には約120名の観客が集まり、個性豊かな3名のパネリストのトークに熱心に耳を傾けた。
1000年先を見るには、1000年昔の渋谷の姿も思い浮かべながら見ていく。
西:最後に、この渋谷ヒカリエの誕生で渋谷の街がどう変わっていくのか、あるいは先の未来、渋谷はどう変わっていくのかを三人の方とお話したいと思います。実はこのパネリストのお三方には以前にインタビューさせていただいたことがありまして、その際に出てきた言葉のエッセンスを、モニターに出させて頂きました。
西:「地域に根ざしたアートプロジェクトの基本は『お祭り』 一過性ではなく、細々でも行事としてやり続けることが大切だ」−これは日比野さんの言葉ですね。渋谷芸術祭時のインタビューだったので、この言葉自体は渋谷ヒカリエとは直接関係がないかもしれないのですが…。やっぱり地域に根差したアートプロジェクトは、渋谷にとっても大事なことなのでしょうか。

日比野:東急さんから渋谷ヒカリエのデジタルサイネージについて、「ここにはどういうコンテンツがあるといいと思いますか」っていう話をいただいたんですが、お正月に事務所近くの金王神社でお正月の輪くぐりみたいなのものを見て、「あ、デジタルサイネージの輪っかと似ているな」と思ったんですね。輪をくぐるというのは、向こう側の違う世界に誘われるというか、同じ一歩でも、輪をくぐったときに何か違うところを通り抜けてきたような印象を受けます。1個の輪っかが、人間のそういうイメージの力を助けてくれる。例えば今日はここの舞台にいますが、この設えによって足袋を履かせていただいて、自分がちょっと違う異次元の空間にいるように感じる。その装置というのが建物であったり、街であったり、電車に乗ったり。そういうことは、輪っかをくぐるのと同じだと思うんですね。
西:はい。
日比野:僕が渋谷に住むようになったのは、渋谷で行われたコンテストで賞をもらったことがきっかけでした。渋谷が文化の一番中心だった80年代から住み始めて、今年は渋谷ヒカリエという、また新しい渋谷のステージができる。その時間の層を、何百年も続いている神社のように、全部つなげていきたいなという気持ちがあるわけです。さっきナガオカさんや小山さんのスペースの話がありましたが、いろんな枝葉をつなげながら「やっぱり渋谷は渋谷で1本スジが通ってるね」という見せ方がないかなと思いますね。渋谷芸術祭も含めて渋谷には今お祭りがいっぱいありますから、そういうものがスパイラルに繋がっていける場を、例えば「8/」の、あのスペースで考えてみるとか…。大きな拠点ができるわけだから、渋谷のアーカイブをしっかりとリサーチして「渋谷とは何だったんだろう」というものを見つけ直し、じゃあ次に何をやろうかということを考える場が生まれればいいなと思います。
西:神社みたいな、時代を越えて受け継がれているもの、それが一つ大事なヒントになるわけですよね。

日比野:ですよね。明治神宮もあるけれども、日本ではああいう鎮守の森というものの周りに人が集まって、縁日をして、お祭りをして…。今、渋谷は毎日、お祭りがあるようなかたちになっていると思うんですが、沿道が商店街になり、大きな通りになるということですから。きちんと温故知新を受け継いでいくことができれば、1本筋が通ったものが見えてくるんじゃないかと思います。20世紀は10年で世の中ってガラっと変わりましたが、3・11以降、やっぱり僕たちも時間の物差しが随分長くなって、10年じゃ大して変わらない、100年でも変わらないかもしれない、1000年単位で見ようよ、みたいなスタンスになってきています。で、1000年先を見るには1000年昔の渋谷の姿も思い浮かべながら見ていくという。時間の目盛りが変わってきたところに、渋谷ヒカリエという次の提案が出てきていると思うんですけども。
西:我々は過去と未来のはざまで何かを考えていかなきゃいけない、というわけですね。分りました。
渋谷はまだ郊外だと思う。でも、それだけ余地がある街だから面白い。
西:次は、山口さんの言葉ですね。山口さんに「渋谷をどうとらえていますか?」と聞いてみたところ、「何も情報を持たずに歩いても楽しめる街で、いい意味でのゴチャゴチャ感を残してほしい」とおっしゃっていました。今はどう思われますか。
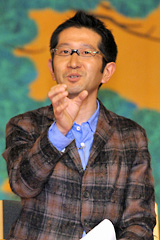
山口:今でもやっぱりそうですよね。渋谷って、いろんなものがぽこぽこ生まれてきて、それでいて取っ付きやすさもあるし、そういう面白さがあると思うんです。渋谷は「若いことが逆に面白さだ」というふうに思ってもいいと思いますね。僕は銀座や日本橋や神田なんかを取材していて、誤解を恐れずに言うなら、渋谷はまだ郊外だと思うんですよね。新宿や池袋もそうなんですけど、都市としての成熟度が、これからという感じがします。例えば、渋谷という名前自体がまだブランドになってないじゃないですか。「銀座何とか」とか「日本橋何とか」っていうものは多いですが、「渋谷何とか」というのはあんまり無い。でも、それだけ余地がある街だから面白いというところがあると思うので、渋谷ヒカリエみたいなきっかけはチャンスだと思う。でも、そこはハードな部分でしかないので、やっぱり僕らが面白がって何かをやっていくという気持ちにならないと、生まれてこないだろうなと思います。「つまらない」というのは誰だって言えることなので、これをいい機会にして僕ら自身が面白がってかかわっていくことが、いいことなんじゃないかなと思いますね。
西:ハードは、ほんとに最先端のものができるわけですから、それをソフトとして、そこにいる人間がどう活かしていくかということが、次の渋谷につながっていくわけですね。
若い人が何かを立ち上げられる隙間があれば、これからも面白い街でい続けられる。
西:では、祐さんの言葉を。祐さんは「渋谷は個人の力で挑戦できる街、スタートラインに立ちたいと願う若者が集う街であり続けてほしい」ということでした。
渡辺:山口さんに近いと思うんですけど、提供されたものをただ消費するという考え方ではなくて、やっぱり自分の力で何かやりたいと思ったときに、小さいけどお店が持てるとか、小さいけど何かを発表する場があるとか…。「渋谷は面白かった」という時代を僕らはアーカイブとして知っているので、これからもそういう街であり続けてほしいと思うんです。わかりやすく言えば、アミューズメントパークと呼ばれるところは、僕はあんまり面白いと思ったことがないんですよ。
西:なるほど。

渡辺:面白いんですよ。それは、すごいスピードの乗り物とかがあるわけだから面白いんだけど、やっぱり与えられたものを順番にこなしていくことしかできない。自分の工夫とか、自分のアイデアを入れられないじゃないですか。だけど、公園とか路地では、自分のアイデアを入れていかないと、逆に面白くないわけじゃないですか。そういう意味で渋谷は、個人のアイデアをいっぱい入れられる街であってほしいなというのは、ずっと思っていることです。例えば(渋谷ヒカリエに出店するような)大きな企業がきちんとしたものを作るというのは、いいに決まってるという言い方はあれですけども、いいわけじゃないですか。だけど、個人の力でしかできない店というのは、絶対にあるんですよ。渋谷だと「雑煮屋鳥居」という、1年中雑煮が食えるBarがあるんですけど。例えば、そういうものは、その店主の工夫でしか生まれないことだと思うんです。そういうことを排除しない街でいてほしいというか、そういう隙間に個人が入り込める余地があってほしい、と思いますね。
西:「個人力」が発揮できる街。
渡辺:個人力が高い人が行こうと思うような街であってほしいですね。
西:最近はどうですか。
渡辺:どうなんですかね。ちょっと話が脱線しますが、飲食店を始めるんだったら、都心から離れろということを、すごく力説している人がいて。つまり腕のある人は都心にいっぱい集まってる、だからおいしい店はいっぱいあると。だけど、例えば国立(くにたち)で一番のもつ煮込み屋をやったら、街の人にものすごく喜ばれる。
西:なるほど。
渡辺:という考え方で、郊外へ出ていくという考え方もあるよね、という話をされていた人がいたんですね。確かにそうなんだけど、さっきの山口さんの話にあったように渋谷は本当の意味で都心じゃないのかもしれないから、若い人が自力で何かを立ち上げられるという隙間があれば、これからも面白い街でい続けられるかもしれないと思いますね。
西:さっきの「8/」の、例えばイベントなんかで。
渡辺:そうです。
西:そういう個人がインスピレーションを受けるような場になっていけばいいですよね。次につながっていくんじゃないでしょうか。
渡辺:そういう気はするんですけどね。
西:渋谷の街は、そういう意味ではパワーは落ちたということも大枠としては言われながらも、未来に向けて、個人の力が発揮できる部分はまだまだたくさん、ほかの街に比べて残ってるわけですから。これをどう活かしていくかということを考えると、個人と渋谷の街のつながりが非常に大事なことなのですね。
渡辺:大事ですね。
一緒に喜びを分かち合いたいとき、人に会いにいくときには渋谷に行く。
日比野:あとやっぱり渋谷って、例えば、スクランブル交差点じゃないですか。スクランブル交差点って、サッカーで、ワールドカップで日本が勝ったりすると。

2010年、南アW杯デンマーク戦の勝利に沸く「渋谷スクランブル交差点」の様子
渡辺:ハイタッチでね。
日比野:ハイタッチで。唯一集まるところなんですよ。世界でも、例えばイタリアが優勝するとミラノのドームの前の噴水に人が集まり、パリでは凱旋門のシャンゼリゼ通りに人が集まるように、自分たちの国民が何か大きなことをしでかしたときに一緒に喜びを分かち合いたい、人に会いたいというときにどこに出掛けるかといったら、日本というか、東京では渋谷に行くわけですよ。
渡辺:広場ですよね。
日比野:人に会いにいくときには渋谷に行く、渋谷に行くと人に会える。きっと建物よりも人がいるというところが、渋谷の面白いところだと思います。だから、人を育てる。僕らが80年代のころは、アートとか、デザインのシーンは公園通りに集まっていて、そういう雑誌文化も含めて渋谷が拠点だった時代がありましたから。
渡辺:ありましたね。
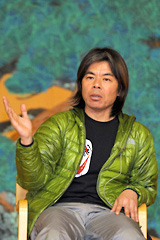
日比野:やっぱり人間を育ててくれる拠点があって、人に会いにいくところが渋谷なのかなと思います。
渡辺:打ち合わせを渋谷でするというパターンも結構ありますよね。何となく集まりやすいし、そういう意味での人に会える。それこそ、個人力の強い人が集まろうと思える渋谷であるべきだという感じがしますよね。
西:それが渋谷の未来への武器にもなりますよね。そういうふうに考えると、渋谷ヒカリエには、人が会う場がたくさんあるような気がします。
渡辺:そうですね。
日比野:「どこどこへ」という方向性を「運動しようぜ」みたいな、「行くぞ」という、そういうネーミングというのは、とても新しいような気がしますね。
西:「ヒカリエ」というネーミングについての話ですね。
全員:(笑)
西:ここから渋谷談議を1時間でも2時間でもできそうなんですけど、残念ながらお時間となりました。渋谷ヒカリエ、オープンまであと64日です。この2カ月、皆さんそれぞれが妄想していただきながら、4月の開業日を楽しみにしたいと思います。それでは、「渋谷ヒカリエからシブヤを考えよう、渋谷文化茶会其ノ四〜男祭り」これにて終了させていただきます。どうもありがとうございました。
全員:ありがとうございました。



ブックマーク |
|

 |
|

