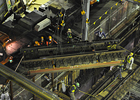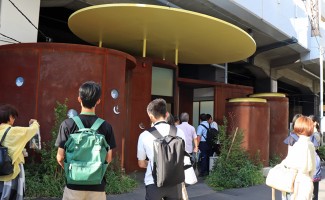奇才監督が伝える映画の世界
奇才監督が伝える映画の世界
梅雨の時期の夕暮れ、突然の雨に慌てて傘を広げる瞬間に「となりのトトロ」を思い出す。また、今では肩身の狭い愛煙家ですが、ごくたまにチェーンスモーカーに出くわすと「勝手にしやがれ」を思い返し、さらに車の窓から見える猥雑な都会の夜に「タクシードライバー」を連想してしまう…。どんなストーリーだったかは忘れてしまっても、日常生活の中でふと印象的だったワンシーンを思い出して豊かな気持ちになることがある。こうした私たちの記憶に残るシーンを持つ作品は、それだけでいい映画と言えるのではないだろうか。 今回はそんな風に唯一無二の世界観で観客を魅了する奇才映画監督たちに着目したい。カルト映画の代表格として知られるデヴィッド・リンチ監督は、写真や版画など映画以外の作品展を渋谷ヒカリエで展開。ジョンレノンや寺山修司が絶賛した「エル・トポ」のアレハンドロ・ホドロフスキー監督は今年84歳にして、自身の半生を映画にまとめあげた。そしてカンボジア人のリティ・パニュ監督は、自身の少年期をもとに土人形を使った独自のアプローチでカンボジアの歴史を紐解く。奇才か、鬼才か、天才か、3人の個性豊かな監督が伝える世界を、ぜひ渋谷で体験してみて欲しい
デヴィッド・リンチ展

- タイトル
- デヴィッド・リンチ展
- 上映場所
- 渋谷ヒカリエ8/内ART GALLERY
- 開催期間
- 2014年6月25日(水)〜7月14日(月)
- 開催時間
- 11:00〜20:00
- 料 金
- 入場無料
- 作 家
- デヴィッド・リンチ
ART GALLERYでは6月25日から、独自の世界観で知られる奇才映画監督デヴィッド・リンチの新作版画・写真を並べる「デヴィッド・リンチ展」が始まった。
デヴィッド・リンチは1946年アメリカモンタナ州生まれ。画家を目指し美術アカデミー後、奨学金を得て1977年に「イレイザーヘッド」を監督。その後、1980年「エレファント・マン」、1986年「ブルーベルベット」などを発表。シュールレアリスティックな作風でカルト的な人気を博し、1990年に「ワイルド・アット・ハート」でカンヌ国際映画祭パルムドールを受賞した。1989年〜1991年TVシリーズ「ツイン・ピークス」は世界中でヒットを記録している。一方で映画のみならず、若いときから絵画や写真、アニメーションや立体作品など、様々な方法で独自の表現活動を続けてきたリンチ。1989年にはレオ・キャステリ画廊で個展を行い、2007年にはパリのカルティエ現代美術財団で大回顧展が成功。日本では1991年に東京の東高現代美術館、近年では2012年に、ラフォーレミュージアム原宿で個展が開催された。
今回は2012年以来2回目の個展で、工房の版画の機械と裸婦をモチーフに撮影した写真シリーズ「NUDE - ATELIER IDEM 2012」と、2012年以降のリトグラフ版画を中心とした近作が紹介される。また東京ミッドタウン・ガーデン内21_21 DESIGH SIGHTでもリンチが出展する企画展「イメージメーカー展」開催予定(7/4〜10/5)。
消えた画 クメール・ルージュの真実

- タイトル
- 消えた画 クメール・ルージュの真実
- 上映場所
- ユーロスペース
- 上映期間
- 2014年7月5日(土)〜
- 上映時間
- 上映スケジュールの詳細は劇場まで
- 監 督
- リティ・パニュ
- スタッフ
- クリストフ・バタイユ(テキスト)、マルク・マーデル(音楽)、サリス・マン(人形制作)、プリュム・メザ(撮影)ほか
ユーロスペースでは7月5日から、国際的に評価の高いカンボジア人映画監督が初めて実体験を元に描いた「消えた画 クメール・ルージュの真実」がスタートする。
監督はリティ・パニュ。1964年プノンペン生まれで、同世代の多くと同じように、自身も父母や親族をクメール・ルージュによる強制労働キャンプで飢餓と過労によって亡くした。13歳でクメール・ルージュから逃亡したパニュは、その後フランスに移住してパリの映画学院を卒業。カンボジア文化が華やかだった時代の写真や映像が全て破棄されてしまったことを発端に、これまで「カンボジア、戦争と平和のはざまで」「虐殺の解明:1億1千万の地雷に反対する10本の映画」など「記憶は再生されるのか」をテーマに数多くのドキュメンタリー映画を監督してきた。
同作はパニュが初めて自身の過酷な人生を土人形に託して描いた作品で、繰り返される人間の愚かさと醜さを、それとは正反対の繊細さと表情豊かな人形で表現。犠牲者の葬られた土から作られた人形たちが、35年前の虐殺の成り行きを語り始め、発掘された映像によってその悲劇が紐解かれていくのだった−−。世界がディスコや「スターウォーズ」に夢中になっていた時代、カンボジアで何が起きていたのか。13歳でクメール・ルージュの大虐殺から生き延びた少年が到達した、かつて誰も見たことがない光景とは?
リアリティのダンス

アップリンクでは7月12日から、「エル・トポ」「ホーリー・マウンテン」など過激な芸術表現で知られる監督アレハンドロ・ホドロフスキーの23年ぶりの新作「リアリティのダンス」がスタートする。
1920年代、幼少のアレハンドロ・ホドロフスキーは、ウクライナから移民してきた両親と軍事政権下のチリ、トコピージャで暮らしていた。権威的で暴力的な共産主義者の父と、アレハンドロを自身の父の生まれ変わりと信じる母に愛されたいと願いつつも、大きなプレッシャーを感じ、また、ロシア系ユダヤ人であるアレハンドロは肌が白く鼻が高かったため、学校でも「ピノキオ」といじめられ、世界と自分のはざまで苦しんでいた…。青い空と黒い砂浜、サーカス、波が運んだ魚の群れ、青い服に赤い靴。ホドロフスキー監督は映画の中で家族を再生させ、自身の少年時代と家族への思いを、チリの鮮やかな景色の中で、現実と空想を瑞々しく交差させファンタスティックに描く。
1995年に事故で息子を亡くして以降、アートを作る理由を考え続けてきたというホドロフスキー監督。タロット・リーディングや、「サイコマジック」という独自の心理療法にも取り組む監督は、同作についてこう語る。「これは人々の魂を癒す映画であり、映画の中で家族を再生することで、私の魂を癒す映画でもあった」

 デヴィッド・リンチ展
デヴィッド・リンチ展 消えた画 クメール・ルージュの真実
消えた画 クメール・ルージュの真実 リアリティのダンス
リアリティのダンス