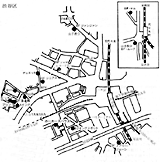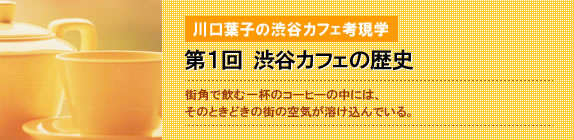

『dimanche ディモンシュ 日曜のコーヒー的なシアワセ。』 アスペクト/カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ編/1995円
街角で飲む一杯のコーヒーの中には、そのときどきの街の空気が溶け込んでいる。
1960年代のジャズ喫茶のコーヒーの味と、2006年のカフェのコーヒーの味はあきらかに違うものだ。人々の味覚の洗練にともなう品質向上という実際的な意味においても、また、コーヒーが何を表現しようとしているかという象徴的な意味においても。
60年代のコーヒーは、言うなれば実存をめぐる思索(あるいは、そんなふり)の味がしていた。私はジャズ喫茶全盛期には間に合わなかったけれど、70年代の最後の年に、どうにか残っていたジャズ喫茶の残滓(ざんし)をかろうじて味わうことができた。
2000年代のコーヒーは、日常生活に見いだす小さな幸福の味がしている。雑誌でもTVでもインターネット上でも、とにかく女性を対象とするメディアのあらゆる見出しに「しあわせ」の言葉が躍っている現在、コーヒーを飲む時間に対しても「しあわせ」は枕詞のように用いられる。夜を導く枕詞は「ぬばたまの」、山を導くのは「あしひきの」、そしてコーヒータイムやカフェを導くのは「しあわせな」。
カフェ・カルチャーの楽しさを教えてくれる鎌倉のカフェ・ヴィヴモン・ディモンシュが、2000年1月に出したフリーペーパー集成のサブタイトルに「日曜のコーヒー的なシアワセ。」と付けたとき、そのシアワセは何かをきちんと表していた。けれども、形容詞というのはあまりにも乱用されるようになると、しだいにその意味を失っていくようだ。しあわせという言葉では、残念ながらもはや何も伝えられなくなったような気がする。それはともかく。
カフェのコーヒーはいつでも、時代の人々が求める気分の味がする。
60年代以降、渋谷にはつねに時代の先駆けとなるカフェが繰り返し誕生してきた。あらためてふり返ってみると、東京カフェの歴史において渋谷のカフェが果たしてきた役割の大きさは驚くべきものだ。年代ごとにまとめてみよう。
ジャズこそが時代を切り拓くものと信じられ、薄暗いジャズ喫茶が全盛を迎えたこの時期、都内のジャズ喫茶のメッカとなったのは新宿と渋谷だった。渋谷では百軒店エリアに有名ジャズ喫茶が集中し、ジニアス、スウィング、オスカー、アリンコ、デュエット、音楽館、ブルーノート、SAV(サブ)、DIG(ディグ)渋谷店などが連日多くの人々を集めていたそうだ。
ジャズ喫茶はマスターの音楽センスと情報量によって、啓蒙的な役割を果たしていた。ジャズに熱狂する人々に優れた音響でレコードを聴かせ、また最新の音楽情報を紹介していたのだ。当時、若い人々の経済力は乏しく、自宅の音響装置も貧弱なものだったから、ジャズ喫茶では何よりも音楽に浸りきることのできる空間が求められ、私語禁止のルールがひろく行き渡っていた。この時代、コーヒーは眉間になるべく深い皺を寄せ、煙草の副流煙をたっぷり吸いこみながら啜るものだったのである。
やがてジャズの終焉が囁かれるようになると、熱い季節は急激に温度を下げていき、偉大なジャズ喫茶の多くは静かにその幕を下ろした。

1989年当時の渋谷・百軒店「ジニアス」店内。
1981年はカフェにとっては記念碑的な年のひとつだと思う。その後のカフェの大きな潮流を作る2つの店が、いずれも1981年にオープンしているのだ。
ひとつは西麻布に誕生したRED SHOES(レッドシューズ)。スタイリッシュな空間と、夜明けまでカクテルと中華系の軽食を提供するスタイルの目新しさが人気を呼び、カフェバー流行の火付け役となった。もちろん渋谷の街角にもカフェバーの一大ブームが到来。私の記憶には、SOHO'S系列各店やチャールストンカフェ、OLD/NEW、サムタイムなどの店が残っている。

昼間から深夜までコーヒーもアルコールも楽しめるというのがカフェバーの定義のひとつだったけれど、正確にはダイニングバーが営業時間を拡大し、昼間もコーヒーと食事を中心に営業するようになったという言い方がふさわしかったのかもしれない。
ジャズ喫茶時代と同様に、この時代にもカフェと音楽との関係は深かった。アメリカで音楽専門チャンネルMTVがスタートしたのを受け、カフェバーのスクリーンにも洋楽のビデオクリップが大量に流れ続けた。この時期に渋谷のカフェバーによく通った人々は、おそらくマイケル・ジャクソンの『スリラー』を通算100回以上は目にしたことだろう(そしてかなりの人々が、スリラーの一部分だけでも踊れたはずだ)。
1981年のもうひとつのトピックは、Afternoon Tea(アフタヌーンティー)の誕生。2000年代のカフェの潮流を考えるなら、こちらのほうがよりいっそう重要な出来事と言えるだろう。渋谷パルコパート3の一角に生活雑貨ショップとカフェを併設してオープンしたアフタヌーンティー。フランスやイギリスのテイストを自由にミックスした美しい空間作りは、ヨーロッパのカフェ文化と、カフェのある生活スタイルへの憧れを強く意識させた。パイン材のアンティークテーブルや、大ぶりのカフェオレボウルなどはこのとき初めてお目にかかったという人が多いことだろう。
80年代のアフタヌーンティーは、雑貨とカフェという非常に親和性の高い要素を組み合わせ、東京カフェスタイルの原型のひとつを作り上げていった。その後のアフタヌーンティーの大規模な全国展開はよく知られるところで、現在でも多くの女性たちに利用されている。

パリ本店ギャルソンのレーモン・コスト氏(右)とジャン・ル・レアネック氏。写真は2004年9月に来日した時のもの。
1989年に渋谷Bunkamuraにドゥ マゴ パリが誕生したのを皮切りに、東京ではフレンチカフェの黄金期が始まった。ドゥ マゴ パリは、名だたる文学者や画家たちが集ったパリの老舗カフェの海外業務提携1号店。渋谷でもパリさながらに青空の下に椅子を並べ、銀のトレイをかかげたギャルソンが行き来する。
フレンチカフェの台頭は、当然のことながら利用者にフランスのカフェ文化を伝授していった。Bunkamuraは本店にならって「ドゥ マゴ文学賞」を創設。現在にいたるまで毎年ひとりの選考委員によって選ばれるユニークな賞で、選考委員の顔ぶれも受賞者の顔ぶれと同様に興味が尽きない。
また、オープンエア、テラス席、ギャルソン、タブリエなどという言葉も、みなこの時期にポピュラーになったものだ。テラス席ではドリンクが運ばれてくると同時に会計をするというキャッシュオンデリバリーのシステムも、この時代におなじみになった。

1989年、Bunkamuraの誕生と同時にオープンしたフレンチカフェの先駆的存在「ドゥ マゴ パリ」

1999年、駅前スクランブル交差点前に「スターバックス」出店。
1996年にシアトルからスターバックスが上陸。コーヒーとカフェオレが主流だった日本のカフェに、エスプレッソベースのカプチーノやカフェラテを浸透させていった。
初めてスターバックスのカウンターの前に立った人々は、一様に「メニューがよくわからなくて注文できない…」という困惑の表情を浮かべていたものの、しだいにドリンクを自分好みにカスタマイズすることを覚えていった。ドリンクのバリエーションの楽しさと、従来の国産コーヒーチェーンにない空間デザインは、あっという間に多くの人をとりこにしていった。
人気の理由のひとつは、コーヒーが苦手な人々でも、スイーツを楽しむ感覚で泡だてたミルクたっぷりのカプチーノを味わえたことだと思う。この時期に個人的に考えていたカフェ金言集の中に、「スタバ好きのコーヒー嫌い」というものがある。コーヒーが飲めない人々にも好まれるカプチーノやカフェラテは、スターバックスから飛び出して2000年代の渋谷のカフェのメニューの主役になっていく。
現在、渋谷にスターバックスは10店舗を数える。渋谷ハチ公交差点前の店舗は、全世界のスターバックスの中で第1位の売り上げを誇るという。

2001年にオープンした和風スタイルのカフェ「ANTENNA」。
2000年代に大きな話題を呼んだカフェブーム。この時期になって東京のカフェは、従来のカフェとは異なる独自のスタイルを持ち始めた。それはフレンチカフェやイタリアのバール、シアトル系カフェなど、海外のカフェを志向するスタイルではなく、個人オーナーがそれらを独自の美意識で解釈・編集し、和のテイストを加えるなどして自分流に表現したもの。2000年代のカフェは、個人オーナーの自己表現の場となったのである。それらの特徴を持つカフェを、私は「東京カフェ」と命名してみた。
東京カフェの第一世代として、後続カフェに大きな影響を与えたのが、渋谷の公園通りに1999年にオープンしたカフェ・アプレミディ。その存在が東京のカフェシーンにもたらしたものや、現在の渋谷のカフェについては、次回の「渋谷カフェの分類」であらためて考えてみたい。
■プロフィール

川口葉子(かわぐちようこ) ライター、エッセイスト。
茨城県日立市生まれ。大学時代より東京都在住。散歩や旅の途中で訪れたカフェは800軒以上にものぼる。1999年末から趣味が高じてサマンサのペンネームでWebサイト『東京カフェマニア』を主宰。雑誌や各Webサイトでエッセイやカフェのレシピを連載中。2006年7月末に『カフェの扉を開ける100の理由』を情報センター出版局より上梓予定。
■著書 『東京カフェマニア〜A Small, Good Thing』(情報センター出版局)
『おうちで楽しむカフェのおいしいコーヒー』(成美堂出版)
『カフェに教わる 10分でひとりパスタ』(宝島社・spring編集部)
『20分でできる ひとりごはん・夏』(宝島社・spring編集部)