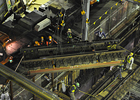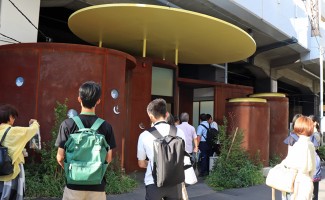「知的障がいのあるアーティスト」に正当な対価が支払われる、そんな当たり前の未来を目指して。
 2017年7月、JR渋谷駅新南口エリアにオープンした「100BANCH」(ヒャクバンチ)は、「100年先の未来をつくるために100人のプロジェクトを支援する」ことを目的としたオープンイノベーションの拠点。2018年にパナソニックが創業100周年を迎えることを機に、パナソニックを中心に渋谷の企業であるロフトワーク、カフェ・カンパニーが協力して構想がスタートしている。
2017年7月、JR渋谷駅新南口エリアにオープンした「100BANCH」(ヒャクバンチ)は、「100年先の未来をつくるために100人のプロジェクトを支援する」ことを目的としたオープンイノベーションの拠点。2018年にパナソニックが創業100周年を迎えることを機に、パナソニックを中心に渋谷の企業であるロフトワーク、カフェ・カンパニーが協力して構想がスタートしている。
2階は一般公募で選ばれたプロジェクトチームが入居し、様々な活動を行うワークスペース「GARAGE(ガレージ)」。 ▲100BANCHでのミーティング風景。
▲100BANCHでのミーティング風景。
これからの時代を担う若い世代とともに、次の100年につながる新しい価値の創造に取り組む。常識にとらわれない価値観を持つ若者たちの「多様なプロジェクト」を、各分野のトップランナーがサポートを行い、メンタリングの機会を通して活動を支援していくという取り組みだ。渋谷文化プロジェクトでは今後、渋谷発の新たなアイデアやテクノロジーが数多く輩出されていくであろう、同実験区に参加するユニークなプロジェクトのひとつをいくつか紹介していく。
第2回目となる今回は、MUKU代表の松田 崇弥(まつだ たかや)さんに話をお聞きした。「知的障がいのあるアーティストが描いた作品」の商品化に携わる松田さんたちは、知的障がいを持つアーティストたちの創作活動の魅力を広く伝えていくと共に、彼らが正当な対価を支払ってもらえる社会を目指して、日々活動を続けています。そんな松田さんたちは渋谷に新たな場をつくって、何をしようとしているのでしょうか。 松田 崇弥(MUKU代表)/1991年5月8日生まれ、岩手県出身、双子の弟、26歳。東北芸術工科大学、企画構想学科を卒業。大学時代、くまモンの生みの親である小山薫堂さんのゼミに所属しており、「入社したいです!」と懇願し、薫堂さんが社長を務める企画会社、オレンジ・アンド・パートナーズに入社。現在も企画・プロデュースを担当するプランナーとして働いている。
松田 崇弥(MUKU代表)/1991年5月8日生まれ、岩手県出身、双子の弟、26歳。東北芸術工科大学、企画構想学科を卒業。大学時代、くまモンの生みの親である小山薫堂さんのゼミに所属しており、「入社したいです!」と懇願し、薫堂さんが社長を務める企画会社、オレンジ・アンド・パートナーズに入社。現在も企画・プロデュースを担当するプランナーとして働いている。
―MUKUの見据える「福祉のかたち」―
MUKUとは、知的障がいのあるアーティストが描くアート作品をプロダクトに落とし込み、社会に提案するプロジェクトです。強烈なアイデンティティを持つ彼らのクリエイティビティを徹底的にブランディングすることで、社会に新しい価値の提案を目指しています。発足から1年半が経過して、六本木アートナイトや国立新美術館での展示会、伊藤忠青山アートスクエアの企画展、FashionRevolutionへの参画、代官山蔦屋書店のフェアなど、数多くの企画に参加しました。いわゆる「福祉」「チャリティー」のカテゴリーから飛び出したプロダクト(商品)をプレゼンテーションし続けることで、知的障がいを持つ方々の創作活動の魅力、パワーが広く認知されることを目的にしています。
|「るんびにい美術館」との出合いが人生の分岐点だった。
_なぜ「福祉施設に所属するアーティスト」に焦点を当てたプロジェクトを始めようと思ったのか、その動機や思いを教えてください。
MUKUは現在5名のメンバーと推進するプロジェクトです。代表である私と、副代表の兄は一卵性の双子なのですが、その上に兄がおり、兄には自閉症という先天性の知的障がいがあります。私たちの母は「福祉」という領域の中で様々な活動に参加する人間でしたので、必然的に私たち兄弟も幼い頃から福祉施設や養護学校、NPO団体等の活動に参加する日々を送っていました。そんなことから自然と、いつかは福祉業界の中で生きていきたいと思っていたのです。
そんな母は社会人2年目の冬、私にこう言いました。
「るんびにい美術館って、知ってる?」 ▲「るんびにい美術館」(岩手・花巻市)にて。左は双子の副代表、松田文登さん。
▲「るんびにい美術館」(岩手・花巻市)にて。左は双子の副代表、松田文登さん。  ▲制作の風景。
▲制作の風景。
岩手・花巻市にある「るんびにい美術館」は、社会福祉法人光林会が運営するアート活動を推進する福祉施設です。そこで、彼らの創作表現を初めて目にしたのですが、それが私の人生の分岐点となりました。
自閉症やダウン症などの障がいの特徴でもある「こだわり」や「脅威的な集中力」が、アートの表現において発揮されるとき、作品の鮮やかな魅力を支える柱になるのだと。そして、これは、彼らにしか描けない世界観なのだと理解すると同時に、強烈なアイデンティティが投影されたアート作品を、広告手法を用いて社会に向けてプレゼンテーションしよう、と思い立った瞬間でもありました。
_なぜ渋谷の「100BANCH」で活動しようと思ったのですか。きっかけがあればぜひ。
発足して1年が過ぎた頃、新メンバーの新しい価値観が入り込んできたことが後押ししました。果たしてアート作品をプロダクト化し、プレゼンテーションし続けることは本当に社会に良い影響を与えることになるのか? 福祉施設とモノづくり現場との代理店になってしまっていないか? 私の興味の領域が、福祉という傘の中で「プロデュース・サービス開発・イベント運営」と大きく広がる一方、そうした迷いも出始めていました。そこで、「100BANCH」というオフィシャルな場所をメディアとして活用して「ブランドからプロジェクトへ」、私たちの活動を一段上に昇華させるキッカケにできないかと思ったのです。
それからもう一つ、渋谷区では「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」を未来像とし、ダイバーシティ&インクルージョンを推進されています。知的障がいを抱えた人、身体障がいを持つ人、高齢者、LGBTなどのマイノリティ、福祉そのものに対する「意識の寛容さ」を持つ街だなと常々感じていましたので、私たちの活動の拠点として相応しいのではないかと考えました。
|「まちといろのワークショップ」で自分と他者の視点の違いに気づく。
_紳士洋品の老舗「銀座田屋」との提携によるネクタイや「小宮商店」との洋傘、「GRANESS Tokyo」とのブックカバー制作をはじめ、多数の事業を展開する松田さん達ですが、これから100BANCHで進めていくプロジェクトを具体的に教えてください。
私たちは「知的障がいのあるアーティストが描くアート作品」と「メイド・イン・ジャパンの職人」とコラボレーションし、徹底的に品質の高い製品作りを心掛けてきました。これからもその思いは変わりませんし、その理念のもと続けて行こうと思っています。 ▲紳士洋品の老舗「銀座田屋」の店内の様子。
▲紳士洋品の老舗「銀座田屋」の店内の様子。  ▲銀座田屋さんと障がいを持つアーティストがコラボしたネクタイ。
▲銀座田屋さんと障がいを持つアーティストがコラボしたネクタイ。
特にこれから力を入れていきたいのは、現在100BANCHで推進している「まちといろのワークショップ」です。施設に所属するアーティストと街に落ちている色を通して、自分の視点と他者の視点の違いに気づくイベントです。  ▲4/29(日)10〜16時、渋谷100BANCHで「まちといろのワークショップ」開催>>詳細
▲4/29(日)10〜16時、渋谷100BANCHで「まちといろのワークショップ」開催>>詳細
信号の赤青黄色、壁のグレー、建物の茶色、冬コートの黒、ツタヤ看板の黄色、コーンのピンク、道路の際にあった緑……街によって色は異なり、そして、気づく色も人によって異なります。同時に色を通して、自分の視点と他者の視点の違いに気づきます。そして、同じ視点があることにも気がつくはず。それは健常者だから、障がい者だからという違いはありません。日常生活では気づかなかった、様々な視点を発見します。本イベントは、プロダクトブランドからプロジェクトへ昇華する大きな起爆剤になるのではないかと期待しています。
_100BANCH以外の活動も含めて、今後の活動を教えてください。
今後は新しいカルチャーを創っていきたいです。例えば、「アール・ブリュット(art brut)」という言葉があります。フランス語で「生の芸術」、日本では「障がい者が創る芸術」と解釈されています。例えば、音楽がカテゴライズ化されてカルチャーに進化したように、「アール・ブリュット」という言葉が持つキャッチーさも、新しい市場を創り出す上で非常に有効であると考えています。プロダクトを作る、イベントを実施する、場所を作る、一過性のコトではなく、何事もカルチャーを作るつもりで推進していきたいです。
※アール・ブリュットとは、フランスの画家ジャン・デュビュッフェ(Jean Dubuffet 1901-1985)によって考案された言葉。加工されていない生(き)の作品、伝統や流行、教育などに左右されず、自身の内側から湧きあがる衝動のままに表現した作品を意味する。英語では「アウトサイダー・アート」と称され、既存の美術や文化潮流とは無縁の文脈によって制作された芸術作品して評価されている。
福祉と社会をつなぐ活動のほか、つい先日ですが、4月22日に思い出の服の祭典「instant GALA 渋谷WWW X」を開催しました。「物語のある服を、着よう。服に物語を、着せよう。愛のない消費を、やめよう」というメッセージが込めて、参加者のドレスコードを「思い出の服」とした音楽イベントで。服への愛着・愛情を喚起することで、ソーシャルグッドなファッションのあり方を発信しました。お陰様で当日は本当に多くの方に参加していただき、大いに盛り上がりました。
instant GALA 公式ウェブサイト
http://www.instantgala.com
_今後、どんな方々に協力・参加してもらいたいという呼びかけがあれば
アート作品の魅力を、プロダクトを通じて多くの人に知ってもらう。そして、社員を雇えるだけの利益を上げ、アーティストにも正当な対価をお支払いする、そんな未来がいつか当たり前になる日を目指しています。なので、ビジネス的な観点から、障がい者の作品をデザインしたモノや、障がい者が作り出した商品が、もっと、もっと、売れるためにはどうすれば良いか、を徹底的に考えられる企業や個人を求めています。そして一緒に市場づくりに挑んでいければと思います。
また私たちは、自分たちが取り扱うアートを「知的障がいのあるアーティストが描いた作品」とカテゴライズしています。「知的障がい」という福祉色・チャリティー色の匂いを感じる言葉を、あえてキャッチーな広告として使用しているのです。「強気」とも「真面目」とも捉えられるかもしれませんが、“あえて”活用するならば、どう編集するべきか、100BANCHでそういうことも含めて共に考えていければと思っています。
 ▲知的障がい者のあるアーティストの作品を取り入れた商品の広告。
▲知的障がい者のあるアーティストの作品を取り入れた商品の広告。
_最後に活動を通じて、松田さんご自身が記憶に残る言葉がありましたら
最近MUKUにジョインしたメンバーに教えてもらった、せんだいメディアテーク館長 鷲田清一さんの「対話の可能性」という詩が最高です。
(以下抜粋)
<対話>は、そのように共通の足場を持たない者のあいだで、たがいに分かりあおうとして試みられる。そのとき、理解しあえるはずだという前提に立てば、理解しえずに終わったとき、「ともにいられる」場所は閉じられる。けれども、理解しえなくてあたりまえだという前提に立てば、「ともにいられる」場所はもうすこし開かれる。対話は、他人と同じ考え、同じ気持ちになるために試みられるのではない。語りあえば語りあうほど他人と自分との違いがより繊細に分かるようにうなること、それが対話だ。「分かりあえない」「伝わらない」という戸惑いや痛みから出発すること、それは、不可解なものに身を開くことなのだ。
100%の思いを込めて「啓発」をする人の正義感って、やはり怖いと思うのです。好き、嫌いは或る日突然逆転するし、良かれと思って嘘をついてしまう日もある。「対話の可能性」という詩に出会い、人は100%理解し合えないという前提に立つようになってから、社会を俯瞰的に見られるようになった気がします。
<取材メモ>
東北の地で培われたご家族との経験を元に、双子の兄弟で代表、副代表を務め立ち上げるMUKUのプロジェクトには、そこ此処に優しく穏やかな趣を感じます。そんな独自の視点を、渋谷をはじめ多地域から発し続けて頂きたいです。
取材協力:100BANCH

砂子啓子(代官山ひまわり)
宮城県仙台市で始まった子育て中心の暮らしを、転居した東京で新たにスタート。育児、家事、防災、仕事、地域活動。多数の興味関心事をミックスし複合的視野を持って生活中。