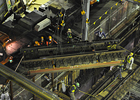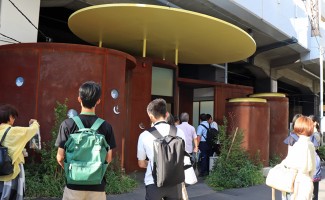「記録性と無意識性」をもつ写真の魅力
本日、東京都写真美術館で開催されている二つの展示を見てきました。一つは、写真美術館が所蔵する昭和の写真を集めた企画展『昭和 写真の1945〜1989』。4回連続して行われる展示の第一部となる今展は「オキュパイド ジャパン(占領下の日本)」をテーマに、戦後すぐの昭和20年代の写真を集めて展示していました。濱谷浩が「敗戦の日の太陽」を写した一枚から始まり、どこか無国籍な街並みを写した奈良原一高の写真で終わった今展からは、かつて存在した人と今も残る土地の歴史をあますところなく伝えてくるものでした。木村伊兵衛の軽やかなスナップショットからは戦後に生きる人々の姿がユーモラスに切り取られ、林忠彦が写した太宰治と坂口安吾の眼差しからは彼らが綴る文章の行間に漂う喜怒哀楽が身近に感じられ、戦後の解放的な空気の中で撮られたヌード写真や実験写真の数々からは「規制に縛られない表現」を手にした作家のエネルギッシュな創作意欲が伝わってきました。英語の標識が街中にあふれ、そこらじゅうに焼け野原が広がるその風景は、紛れもなく自分が生まれたこの国の思い出の写真なのだということを実感しました。痛ましい光景も多々あったものの、全体の印象としては、戦後の空白の時間を経て、復興に向けて必死で生きる人々の活気やたくましさを感じさせるものでした。
 笹本恒子「銀座4丁目 P.X.」シリーズ「昭和・あの時・あの人」1946年夏頃
笹本恒子「銀座4丁目 P.X.」シリーズ「昭和・あの時・あの人」1946年夏頃 林忠彦「太宰治」 1946年
林忠彦「太宰治」 1946年もう一つは佐渡島の自然を10年以上にわたって撮り続けた天野尚による写真展『佐渡─海底から原始の森へ』。四季折々の表情を捉えた原生林や海岸の写真からは、日本の伝統美を感じさせる風景が数多くありました。水墨画を思わせる端正かつミニマルな波、浮世絵のような鮮やかな色彩を放つ紅葉、幽玄の美を感じさせる雪の積もった枝、深遠かつ甚大な野生の森。最大で8×20インチという超大判カメラを用いて撮られた写真には、「自然の姿を克明に記すために大判カメラを用い、一木一草が自然を成り立たせていることを明らかにしたかった」という作者のコメント通り、生命力に溢れた自然の様子が細密に写されていました。
 『佐渡─海底から原始の森へ』展より。キャプションには「幹回り11mを超える巨大杉。その樹齢は千年以上だが、あまりに古いため正確な樹齢を知る人はいない。」と記されている。
『佐渡─海底から原始の森へ』展より。キャプションには「幹回り11mを超える巨大杉。その樹齢は千年以上だが、あまりに古いため正確な樹齢を知る人はいない。」と記されている。二つの展示から強く感じたのは、写真の「記録性」の力と同様に、ヴァルター・ベンヤミンが言う「写真が持つ無意識性」のおもしろさでした。絶えず視界のどこかにフォーカスする人間の目とは違い、ファインダーに収められたすべての景色を取捨選択せずフラットに映し出す写真表現の無機質な側面が、この二つの展示では強調されているように感じました。『昭和』展の撮影者がカメラを向けた先に無意識的に映り込んだ、看板の文字や煙突の煙や放置された建築資材などからは、そこにある音や匂いや湿度を想像することができたし、『佐渡』展の「千手杉の森」の写真には、仮に自分が同じ景色の前に立ったときにはきっと意識すらしなかったであろう足元の草木一本一本の細やかなディテールや木の幹に付いた傷跡が、大判カメラ故の精密さではっきりと描写されていて、「自然とは小さな草木や土や石から構成されている」という当たり前の事実に気がつき、驚かされました。一枚の印画紙の中にその時代・その場所でしか持ち得ない表情や熱気といったものがたっぷりとつまっている「写真」の魅力に改めて触れ、写真集などからは決して伝わってこない「写真表現の原点」に立ち返ったような二つの展示でした。
美術館を出た後、目が慣れない風景に違和感を覚え、クリーンなレンガ造りの建物やきちんと整えられたガーデンプレイスの街並みを美しいとは思えなかったのは、それまで昭和の街と原始の森に浸っていたからでしょうか。東京の下町で生まれ育った自分の目には、馴染みがあるのは写真の中で生き続ける風景の方でした。

編集部・M
1977年東京の下町生まれ。現代アートとフィッシュマンズと松本人志と綱島温泉に目がないです。