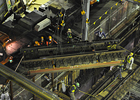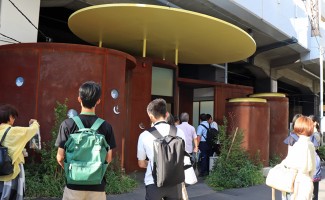★『ベンジャミン・バトン』
ヴィヴィアン佐藤評★
デビッド・フィンチャー×ブラット・ピット三作目(『セブン』、『ファイトクラブ』)とくれば、何が何でも食指が動く。今更ながらブラピの尊顔を拝んできた。 映画宣伝・コピーの言うところの「人生に一度の感動作」でも、「人生は素晴らしい」作品でもなく、実は「数奇な人生」の男の物語でもない。
映画宣伝・コピーの言うところの「人生に一度の感動作」でも、「人生は素晴らしい」作品でもなく、実は「数奇な人生」の男の物語でもない。
『ベンジャミン・バトン』はフィンチャーが『ファイトクラブ』で、アニメ映画にポルノ映像を差し込み、高級ケータリングに小便を混入させるいかさま映像技師タイラー・ダーデン(ブラット・ピット)、彼自身が作った映画の様だった(タイラーは主人公ナレーターが作り出した分身/妄想で、物語は原作者パラニャークが作り出したフィクション)。子供が見る映画を「ファミリームービー」というジャンルで括るなら、そこにポルノを差し込む。その「隠し味」をも含めて「ファミリームービー」と言わせることだ。そんな仕上がり。ハリウッドの「オスカー作品賞」というジャンルの映画があるとしたら、帰納法的に「素晴らしい感動的な映画」の中で悪趣味風味をを知らず知らずに味わせる。「オスカー作品賞」ジャンルの映画として大手製作会社と作り、大々的に大衆に訴え、毒を隠し味として差し出す悪ふざけはタイラー・ダーデンと全く同じだ。『ベンジャミン・バトン』の監督はタイラー・ダーデン自身だ。タイラー・ダーデンはいまだ生き延びていたのだ。
日本での映画上映初日前後、15秒テレビCMが幾度となく流された。予測を全く裏切ることなく、実際の映画の内容はそれ以上でもそれ以下でもないものであった。167分の割と長編映画は15秒で事足りるのだ。物語を追ったり感情移入する事だけを考えればの話だが。。
ベンジャミン・バトンは生まれながらにして80歳の肉体を持って生まれ、徐々に若返っていき、最期は赤ん坊として死ぬ。これだけを聞けば確かに数奇な生体だが、これは「もしも」の話。病室で死にゆく母親が実の娘に、バトンの日記を読ませ、自分もその記憶を重ねていく。。しかしバトンの肉体は確かに稀有だが、その病室の中での思い出話を語る「行為」も、近づいてくる「ハリケーン」も、「第一次世界大戦」も、「アメリカ」も、劇中の同じ作り物の要素である事には変わらない。バトンの肉体だけが数奇なわけではない。世の中の映像というもの自体が完全なフィクションである事を忘れてはならない。我々はスクリーという布とそこの上に投影される光を見ている事だけが真実なのだ。
ベンジャミンとデイジーは出会ってから、21年目に再会する。ちょうど二人の見た目は同じ位の年齢だろうか。ベンジャミンの古巣の部屋で二人きりになり、両者が映り込む「鏡」。この「鏡」の中の像こそが、この劇中唯一の「真実」となる。砂時計のくびれた折り返し点の様に、この瞬間のみが「いま(永遠)」を映し込んでいる。
ヤン・ファン・アイクの『アルノルフィニ夫妻の肖像』。鏡の上には「ヤン・ファン・アイク、ここにありき」と印されている。
ベンジャミンもフィクションである。全ての思い出も歴史も何度でも書き換えることができる。ベンジャミンは劇中、実在していないのかもしれない。 そもそも記憶の遠近法とは曖昧である。瞬間ではなく、もし時間というものが連続したものであれば、近く記憶のほど鮮明のはずで、遠い昔ほど不鮮明である。脚色された思い出の場合はその反対となることもあるだろう。。。 少年から老人へと代わるベンジャミンの肌質は、デイジーのそのときの彼女の記憶の脳の表面と同質となる。ベンジャミンの皮膚は、デイジーの思い出の脳と限りなく擦り寄り、同化する。
生きている人間は必ず死に、死んだ人間は何度でも様々な形で蘇るものだ。これは劇中でも現実でも同じ事なのだ。

ヴィヴィアン佐藤(非建築家)
非建築家、アーティスト、ドラァククイーン、イラストレーター、文筆家、パーティイスト、、、と様々な顔を持つ。独自の哲学と美意識で東京を乗りこなす。その分裂的・断片的言動は東京では整合性を獲得している。。。なんちゃって。