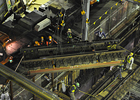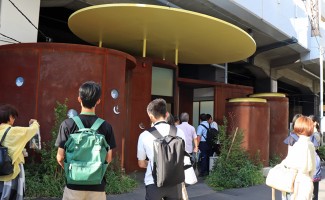今年4月の渋谷区長選で、無所属立候補ながら初当選を果たした長谷部健さん。元広告マンであったクリエイティブなセンスを生かし、「green bird」「シブヤ大学」「宮下公園のリニューアル」「渋谷・表参道ウィメンズラン」など、今までに「まち」と「ひと」を繋ぐ数々のプロジェクトを手掛けてきた。また今春、渋谷区が初めて施行した「同性パートナーシップ条例」では、発案者として一躍脚光を浴びるなど、その精力的な活動は区外や世代を超えて高い注目を集めている。「100年に一度」といわれる大規模開発が進む渋谷駅周辺や、2020年の東京オリンピックの開催など、渋谷が大きな転機を迎える中で、新区長である長谷部さんは「渋谷のまちづくり」の課題と未来の方向性をどう捉えているのだろうか。「フルマラソンを3時間7分で走り切る」という体力とやる気がみなぎる、43歳の若きニューリーダーに今の心境や、渋谷で実現したいアイデアなどについてじっくりとお話を聞きました。
広告マンから転身し、渋谷のソーシャルプロデューサーを目指す
_長谷部さんご自身は渋谷の魅力をどう捉えていますか?
日本の中で最先端のカルチャーがそろっている都市で、暮らしてとても気持ち良いまちです。僕自身、サラリーマン時代に1年間だけ、福岡で暮らしましたが、それ以外は40年以上も原宿に住んでいますから。
_時代は変わっても原宿はティーンズの情報を発信し続けています。住人として見続けてきて、その要因をどう捉えていますか?
原宿の発展には、2つの大きなタイミングがあったと思います。一つは戦後、現在の代々木公園に在米軍住宅地「ワシントンハイツ」があったことでしょう。アメリカ人向けの土産屋さんや陶磁器のお店などが表参道の参道沿いに点在し、現在のラフォーレ原宿の場所も、かつては教会でした。僕の親や、その上の世代の人たちにとっては、そこで初めて外国人文化に遭遇したわけです。また外国人に対しても、明治神宮の「和の文化」に洋風なトッピングが加わった表参道の雰囲気は、和洋折衷ですごくクールな印象を与えていたのではないかと思います。
次のブレークスルーが「東京オリンピック」です。道が整備されて、原宿にはコープオリンピアやセントラルアパートなどの高級マンションが建ち、そのころには同潤会アパートもいい味を出し、まちが発展していく。新宿や渋谷に大企業が集まり、メガなまちとして成長する一方で、その間に挟まれた原宿や表参道には、一旗揚げようという僕らの親世代の若者たちがやってきて。いわゆる、マンションメーカーと呼ばれた彼らは、安い家賃のマンションの一室で洋服のパターンを起こし、それがゆくゆくのDCブランドの前身になったりとか。そういう成功者の出現が相乗効果となり、だんだんとクリエイティブ・クラスの人びとが集まる場所になったという経緯があります。こうした歴史的な背景から、今日まで続くカウンターカルチャーの生まれやすいまちが形成されたのだと思います。
_それは、大人が若者に「寛容なまち」ということでしょうか。
そうだと思います。カッコつけた言い方ですが、(表参道の)ケヤキも四季折々で変化するじゃないですか。そういう意味で常に変化していくまち。ただ、守らなきゃいけないものはしっかりと守るという、両方が成り立っている東京で唯一のところじゃないかなと思う。地元民なので、ちょっとそういう自負はあります。
_大学卒業後は、バリバリの広告マンとして働いていたわけですが、なぜ、そのポジションを捨て、区議会議員に出馬されたのですか? その動機を教えてください。
「議員になろう」なんて、自分の人生設計の中で考えたことは全くなかったんです。僕のことを担いだのは表参道の商店会「欅会(けやきかい)」の人たちですが、最初は「はっ?」みたいな。当時の僕からすれば、「政治家はカッコ悪い仕事だ」と思っていたぐらい。たとえば、合コンに行ったとして、「博報堂と区議会議員の名刺を見せたら、どっちがモテる?」みたいな、世の中そういうもんだよね(笑)。
その一方で、「いつかどこかで独立して何かやろう」など、割と僕ら世代は起業精神旺盛で、同じ年次入社の3分の2くらいの人が辞めています。だから、会社を辞めることに全くネガティブな意識はなくて、いつか辞めて、クリエーティブエージェンシーを立ち上げたいという気持ちがずっとありました。また、ちょうど時代は90年代後半で、広告業界では、コンドームをバーンと並べてエイズ予防を訴えたベネトンの広告キャンペーンなど、企業の社会貢献やCSRという言葉が出始めたころ。そういう社会にインパクトを与えるエッジの効いた広告を、プロデューサーとして手掛けられたら楽しいだろうなと思い、「仲間と一緒に一旗揚げよう」と本気で考え始めたときに、並行して欅会の人たちからも「やらないか」って話がやってきて。最初は一笑に付したのですが、商店街の人たちもなかなか言葉が巧みで、「おまえはプロデュース、プロデューサーと言うけど、おまえにやってほしいのは表参道のプロデュースや、渋谷のプロデューサーなんだ! 政治はソーシャルプロデュースだ!」というわけです。ちょっと単純かもしれませんが、「ソーシャルプロデューサーか、ちょっといいかも」と琴線が触れたところもあり、そのとき、ちょっと酔っ払っていたのもあるのですが(笑)、その気分のままに「俺やるよ」と電話したのが始まり。「おだてられて木に登った」ところはありますが、ソーシャルプロデューサーという立場で、原宿や渋谷で仕事ができるのは、自分のキャリアにとっても非常にいい経験になるだろうなと感じていました。当時、もし結婚して子どもがいたら、この決断はなかったかもしれません。

グリーンバードがゴミ拾いボランティアを行っている表参道の歩道
僕はタイプ的に「0」を「1」にするのが得意な人間なのかなと思う
_議員時代は本当にいろいろ活動されていて、春の小川やグリーンバード、シブヤ大学とか、さすが広告マンだなというキャッチのうまさや、先見性のあるテーマが多いと思うのですが…
もともとgreen bird(グリーンバード)は、実際に商店街の掃除活動に参加してみて、大変ながらも楽しくかった経験をきっかけとし、ソーシャルプロデューサーとしての一番初め作品ぐらいのつもりで始めたものです。僕は高校生くらいまで、掃除が嫌で嫌でしょうがなかったんですよ。毎日、学校に行く前に実家の玄関先を掃除させられていたのですが、こんな姿を後輩にでも見られたら、学校での自分のアイデンティティが崩壊してしまうんじゃないかと。とても最低な話なのですが、とにかくゴミを拾わずに、排水溝にぶわーっと素早くほうきで落として済ませていたくらい。それが大人になって表参道の掃除をやってみたら、なんて楽しいのだろうって。やはり、やらされるのではなく自発的にやるということや、知らない人が「偉いわね」とか「おはよう」とか声かけてくれたりすること。それから当然、汚かったストリートがどんどんキレイになっていくのは、とても爽快なものだと気が付いたわけです。これを共有共感できれば、もっと多くの人びとを集められるんじゃないかと。

そこで「ポイ捨て格好悪くね?」というキャッチやロゴ、ユニホームなどを含めた「ポイ捨てしない人を増やすキャンペーン」を商店会に企画提案したところ、「こういうのを待っていた!」とみんな大喜びで。でも「待てよ、一体誰がやるの?」みたいな話になって、じゃあ、僕がやるしかないのかという。今思うと大きな出発点で、「ソーシャルプロデュースって、こういうことだな」という確信を得るきっかけとなりました。「課題をコミュニケーションで解決する」というのは、博報堂の時にすり込まれていたことで、「シブヤ大学」も似たような発想で、カッコいい大人をつくろうと思ったのが発端です。今の子どもたちは、草食系とか揶揄する人もいるかもしれないけど、そのへんのおっさんよりもよっぽど地球環境を考えている。その子どもたちが憧れるような大人をつくらないと、結局、問題は解決しない。たとえば、「カリスマ美容師の上手な頭の洗い方」を学ぶとか、明治神宮の「100年の森」の授業を大正時代の英知が詰まった森の中で聞くとか…。渋谷区には先生になりたい人もたくさんいるし、社会貢献したいというマインドを持つ人も多く、考えてみたら、渋谷区そのものが大きなキャンパスだったり、大学みたいな存在じゃないかと。生涯学習とか、カッコいい大人をつくるという「まちの空気」は、法律や条令をつくるだけじゃできないもの。もちろん区議として法律や条令にも絡むのだけど、ソーシャルプロデューサーなら、もっとそれ以外のこともできるはずだと考えて取り組んできました。
_瞬発的なアイデアもさすがですが、これだけ長く持続してきたというのはすごいことですね。
「長谷部健被害者の会」というのが出来ていましてね(笑)。自分一人じゃできないけど、みんなが一生懸命それをやってくれるわけです。でも、それは僕も、みんなも楽しくやっているから出来ること。僕はタイプ的に、今まで自分を「1」から「10」にする人間だと思っていたのですが、意外に「0」を「1」にするほうが得意なのかもしれません。世の中はこういう人が意外に少ないんですよ。それがうまくいくと石油を掘り当てちゃうタイプなのだけど、ただ、世の中は、その石油を精製して売る人のほうが儲かるわけです。本当は「1」から「10」にして大金持ちになるはずだったのだけど(笑)。

新区長である長谷部健さんに区長室でインタビューを行いました。