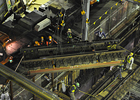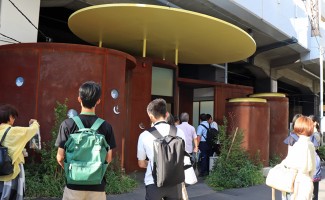80年代に渋谷・桜丘町に「ユーロスペース」をオープンして以来、ミニシアターの草分け的な存在である堀越謙三さん。「渋谷の大規模再開発の今だから、戦わないと」と語気を強める堀越さんは、街の再開発に伴い、アヴァンギャルドやサブカルチャーなど、渋谷の街が育んできた独自の文化が消え失せてしまうのではないかと危惧する。こうした背景の中でカルチャーの火種を残すべく、今秋、円山町にライブホール「ユーロライブ」をオープン。落語やコントなど、ライブエンターテイメントを中心に新たな文化の発信を目指していくという。今回のキーパーソン・インタビューでは、30年間にわたって渋谷を見続けてきた堀越さんを迎え、80、90年代のミニシアター・ブームから今日の映画産業の衰退、さらには文化発信の新拠点「ユーロライブ」を立ち上げた真意をじっくりと語ってもらいました。
映画を仕事にしようなんて、思ってもいなかった。
_大学卒業後、ドイツ留学されていますが何を学んでいたのですか?
留学というほどでもないのですが、もともと大学では独文科でしたので。僕は全共闘より一つ、二つ上の世代で、大学には後半行っていませんでした。要領よく企業に就職すれば、企業に買い取られたやつと、ひんしゅくを買ってしまうという時代でした(笑)。ともかく日本にいられなかったので、向こうに行っただけです。その後、ドイツで起業しちゃったので、足かけ4年ぐらい。
_起業って、何をされていたのですか?
日本航空に依頼されて、「欧日協会」という旅行代理店を立ち上げました。当時、パリには日本人の若者たちがたくさんいましたが、ドイツにはほとんど人がいなかった。居ても、学生なら大学院生が最低レベルで、あとは企業の派遣や研究者など、身元のはっきりした人ばかりで、そういう日本人の一時帰国や家族の呼び寄せのためのチャーター便を飛ばす仕事です。
_映画との出会いは?
僕は45年終戦の生まれですが、ヴェンダースとか、ファスビンダーたちと全く同世代。代理店の仕事をしていたときに、そういう人たちがアクションシアターという演劇をやったり、映画を撮り始めるなど、ドイツに新しい波が生まれ始めたころ。その彼らの映画を日本に紹介したのが、映画に関わる初めての仕事でした。正直、それまで映画を仕事にしようなんて、思ってもいなかったですけど(笑)。
_映画館を構えたのは、どうしてですか?
パリとロンドンに旅行代理店の支店をつくって、東京になかったのでつくるために帰ってきまして。帰国後、旅行会社のかたわら、映画の上映会やイベントなどを行っていましたが、やはり拠点がないと疲れるし、本業にも差し障る。そこで、ユーロスペースをオープンしたわけです。頼まれて始めた旅行代理店や、レストランなどは上手くいっていたのですが、映画だけは全然上手くいかなくて。結局、会社を日本航空に売り払ったり、レストランを売ったりして今日までユーロスペースを30年維持し続けてきました。
文化を発信するなら、ジァンジァンのある「渋谷」だろう。
_映画館の立地として「渋谷」を選んだのは?

かつて公園通り・山手教会の地下に若者文化に大きな影響を与えた「ジァンジァン」があった。
やっぱり多目的スペース「ジァンジァン」ですよ。文化の発信をするなら「渋谷」だろうと。最初は1スクリーン、80席の劇場だったから、某映画評論家には「いい試写室ができたね」とか揶揄されましたけど(笑)。今だからこそ、80席という劇場は当たり前ですが、あのころは1,000席とか大きな映画館が多く、300席でミニシアターと言われていたくらい。一応バブルの前兆ですから、皆さんが考えるほど桜丘町といって家賃は安くなかったんですけど。
_その後、ミニシアターが渋谷に集積して「ミニシアター・ブーム」が起きますが、そのきっかけは何だったのでしょうか?
80年代のセゾン文化の影響が強いと思う。まず、シネヴィヴァンが六本木に出来たのは大きいし、それから渋谷ではシネセゾンやパルコ劇場、パルコ・スペースPart3、シードホールができた。70年代まではアヴァンギャルドか、アングラなんですよ。両方ともにマイナーカルチャーなんだけど、どちらかといえば、アヴァンギャルドが洗練されたもので、アングラが土着なものというイメージが強い。こうした中で80年代に西武、セゾンが洗練されたアヴァンギャルドな方向に文化を引っ張って行ったのが、ミニシアター・ブームのきっかけだと思う。また、映画ファンだけじゃなくて、アート全般も取り込むことが出来たのが要因でしょう。やっぱりアングラというと来る人を選んじゃうよね、泥くさいから。僕らは、あのころ「アートコンシャス」って言葉を使っていて、先駆的なものであれば、美術であろうと、映画、ダンス、演劇であろうと追いかける人たちが、首都圏に約10万人くらいいましたね。その一方で印象派美術展に行くと馬鹿にされるという…。
_その当時、ヒットした作品で印象深いものはありますか?
ユーロスペースは自分の劇場で公開するほか、買い付けてきた作品を他の映画館に配給する業務もしています。その中で、今までで一番ヒットしたのが、92年に公開したレオス・カラックスの『ポンヌフの恋人』です。この作品はシネマライズに配給し、6カ月間のロングランになりました。初日の記録、1週間の記録など、あらゆる記録を作っちゃって。ライズだけで1億5千万円ぐらい、全国で2億5千万円くらい。そのへんがうちのピークですよ。その後、うちが持っていたライズでの記録は「トレインスポッティング」に、恵比寿ガーデンシネマでのヒット記録は「スモーク」「ボーリング・フォア・コロンバイン」にすべて塗り替えられちゃたけど…。
ミニシアターじゃ食えない、ユーロスペ−スも潰れていたかも。
_売上げは、劇場以外に二次利用のDVDやオンデマンド配信などがあると思うのですが、そちらのほうが儲かりますか?
昔レンタルショップでは、1本1万円幾らで買ってくれたので、2,000本オーダーがあれば2,000万円の売上があったわけです。それも昔の話で、今アート系映画は前払い金をほとんどもらえず。しかも、「DVDをつくって納品しろ」って言うわけで、天と地の差ですよ。現在のレンタルの仕組みは、レンタル代が300円で、レンタル本部が100円、お店が100円、そして僕らに100円しか来ないんだから。何億円もかけて作っても1回しか来ないっておかしいでしょう(笑)。だから映画は、今90%以上が赤字なんですよ。年間に日本映画だけで大体600本から700本作られているんだけど、そのうち劇場公開されているのは500本くらい。さらに回収できているのは、たぶん25本がいいところ。先日、フランス映画社が破産してしまいましたが、レンタルの二次利用でお金が入ってこなくなっちゃったのが大きな原因ですよ。
_配給会社だけではなく、ミニシアターもバタバタと閉館に追いやられていますね。
配給会社は、シネコンに断わられた作品しかミニシアターに配給しないから。電話一本で全国上映できるので、効率いい。ミニシアターというのは一館一館連絡しなきゃならないから、シネコンの出現で商売のやり方が変わってきたということです。
_ユーロスペースは、シネコンに配給はしないんですか?

2006年に桜丘町から円山町に劇場を移転した。
うちは全国のミニシアターの象徴的な存在でもあるので、彼らを優先します。よく地方のミニシアターが相談に来るけど、「あなたが給料を取らなければ、やっていけますよ」と言います。一番人件費が高いのは本人だからね。だから今の仕事を辞めるなと、辞めないで誰かにやらせていればやっていけるけど、自分が勤めている会社を辞めて「映画から自分の生活費を取ったら潰れるよ」って言うんです。現在、ミニシアターの売り上げは90年代の半分くらい。うちだって桜丘町に居たら、あと3カ月ぐらいで潰れていたと思う。僕があそこで20年間やってこられたのは、20代から別の事業をやってきたから。とてもじゃないけど、映画青年が維持できるもんじゃない。
_今後、ミニシアターは益々減っていくのでしょうか?
減っていくだろうね。スタッフは食えないし、結婚できないし。今みんな後継者問題で悩んでいるんだけど、「あげるよ」と言っても、誰ももらいたがらない。経営者じゃなく従業員だったらずっと働くけどって。だから、それを多少社会で支えていかないと本当に無くなっちゃう。でも、それを政府が支援するわけにはいかないから、新しいファンドの形を考えるしかないかなと思っているところ。この間、若い人が尾道で閉館したミニシアターを復活させたんだけど、人口が10万人しかいない、あの場所ではどう考えても無理なのよ。最低でも50万人以上いなきゃ難しい。でも、どうしても彼女がやりたいというので、クラウドファンディングで250万円ぐらい資金調達して、中古デジタルシステムを入れて存続させた。そういう形ならお金が集まることもある。