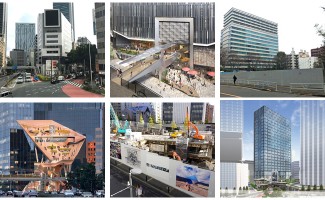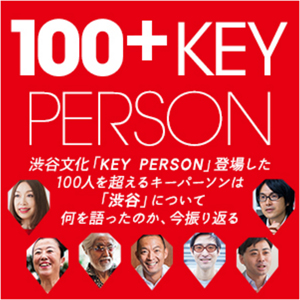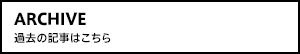ミニシアターの先駆け的な存在として、渋谷のカルチャーシーンに大きな影響を与え続けてきたシネマライズ。その経営を手掛ける頼光裕さんに、渋谷の街が持つ独自性や、ミニシアターや映画界の現状、さらに今後の渋谷が採るべき針路などを聞いた。
ミニシアターの先駆け的な存在として、渋谷のカルチャーシーンに大きな影響を与え続けてきたシネマライズ。その経営を手掛ける頼光裕さんに、渋谷の街が持つ独自性や、ミニシアターや映画界の現状、さらに今後の渋谷が採るべき針路などを聞いた。――長年、渋谷を見つめてこられた頼社長にとって、この街の魅力はどのような点にあると思いますか。 自然発生的なショップが集まって昔からミックスカルチャーが根付いているところが面白いと思いますね。さらに、レコードにしても洋服にしても、個々のショップが頑張ってマニアックなものを揃えているから若者を惹きつける魅力もある。昨年の夏、パルコの周辺に上海や韓国から来た若者が群がっているのを見て驚いたことがありました。ニューヨークでも、今は日本がクールに映っていて、その中でも渋谷や原宿が特にクールに映っているようです。それから渋谷は計画的に造られた街ではないので、「地に足が付いている」という良さもあると思いますね。最近の大規模商業施設は、施設内の動線を工夫しているみたいだけど、あまり歩いていて楽しいとは感じません。「人間が歩いて楽しい街」、それが渋谷の魅力じゃないでしょうか。

――そもそも頼社長と渋谷との関わりは、いつから始まったのでしょうか。 大学時代には渋谷が乗り換えの駅だったから、しょっちゅう降りて遊んでいましたね。当時、洋盤のレコードは道玄坂のヤマハくらいにしかなかったから、そこに通ったり、百軒店のジャズ喫茶や、公園通りの喫茶店「時間割」にたむろしたり――。その頃から渋谷には文化の匂いみたいなものは漂っていましたね。それが今の若者には、渋谷に行けばレコードでもジーンズでも「何か特別なものが手に入る」という形で引き継がれているんじゃないのかな。
――上映する映画は、どのような基準で選んでいるんでしょうか。 これという基準はないですね。お客さんを満足させられると自信が持てる内容なら、ジャンルにこだわりません。ですから、作品によって客層はさまざまですよ。一番、意外だったのが『ムトゥ 踊るマハラジャ』。予測がつきにくい中、僕なりにすごい映画だと思って上映したら、若者だけでなく、巣鴨に通っているようなおばちゃんも大勢集まってくださって大ヒットした(笑)。あと、『ヒトラー 〜最期の12日間〜』のときは、予想以上に高齢の方が集まりました。昼間は、それこそ高齢の方でいっぱいでしたが、夜の回には、それこそパンクの格好をした若者が集まるわけだから、一つの目標としている世代のミックスという点では成功でしたね。

――今後、渋谷の街を活性化させるためには、何が必要だと考えていますか。 個々のショップの努力とその集積が街全体の雰囲気を醸成している点は、渋谷最大の特徴です。ですが、厳しい言い方をすれば、それしかないとも言える。個々がもっと頑張ることが必要で、いいものを増やして愚にも付かないものを渋谷から追い出すくらいでないと。常に「渋谷は何かがありそうだ」という匂いを醸し出していなければ、

また(渋谷に限りませんが)これからは「文化」がちゃんと事業になる時代にしていかなければいけませんね。トロントやカンヌのように、映画祭自体が産業になっており雇用の機会を生み出している例もある。それと、若いころから渋谷に根付いてクリエイティブな活動をしている人たちが他の街に移り住んでしまっているようだけれど、それは、クリエイターへの支援の仕組みが少ないためだと思います。クリエイティブな活動をしている人たちが生活しやすい環境をつくることも渋谷の街にとっては重要だと思います。
それから、客層に幅をもたせることも重要じゃないでしょうか。渋谷は大人の受け皿が少なすぎる。若いうちは通うけど大人になったら卒業というのでは、これからはしんどくなりますよ。だから、周辺にオフィスを誘致したり、大人が満足できるような飲食店を増やしたり、また良い店は残す努力をするなど、世代をミックスさせるための取り組みに本腰を入れなければいけないと思いますね。
シネマライズの情報はこちら
■プロフィール
頼光裕(らい・みつひろ)さん 東京都中野区生まれ。ミニシアター「シネマライズ」の運営を手掛ける泰和企業代表取締役。
1986年(昭和61年)、宇田川町にライズビルを開業、1996年に独立系ミニシアターとなり
2004年にはデジタル対応シアター「ライズエックス」をオープンした。